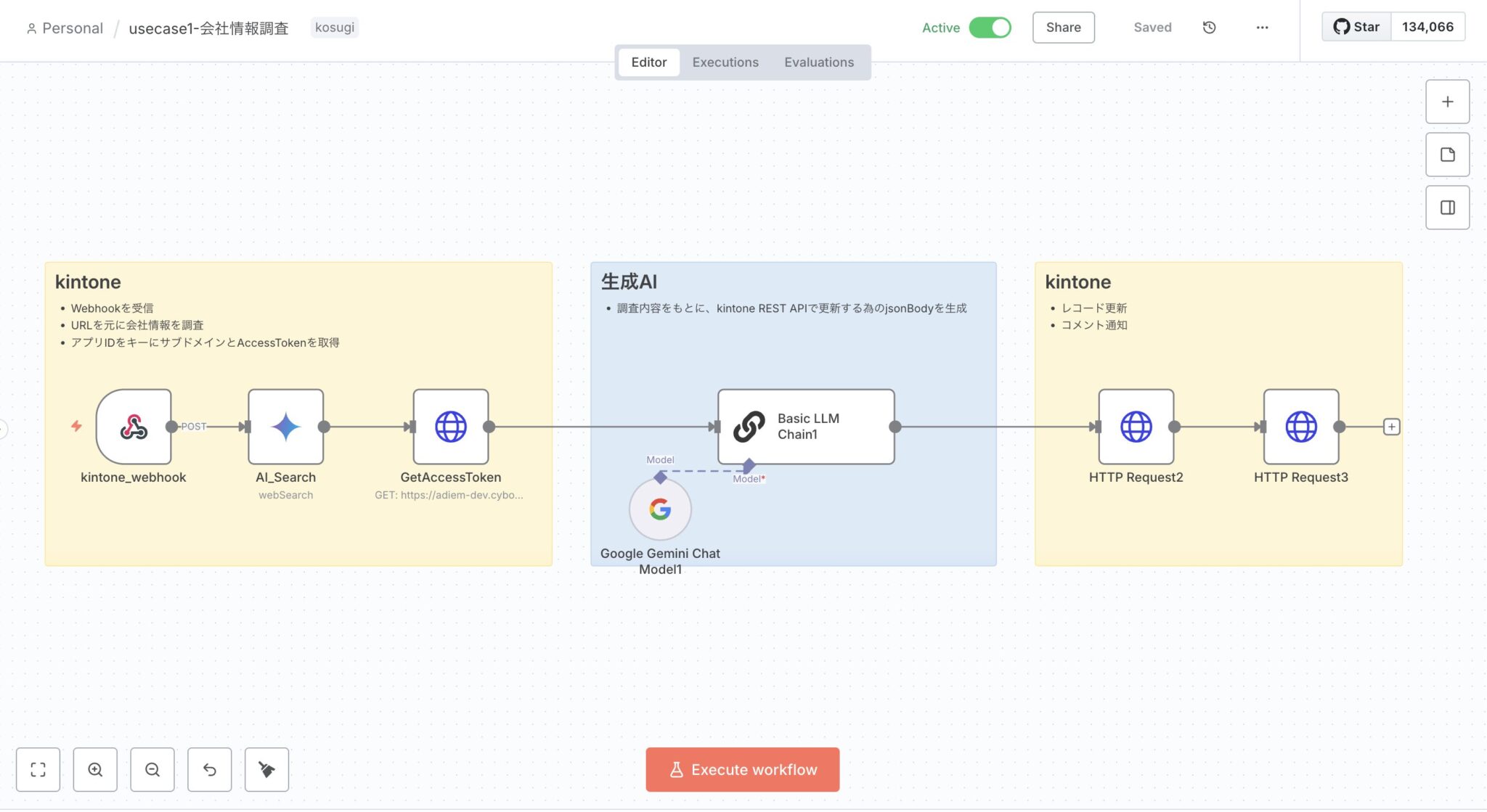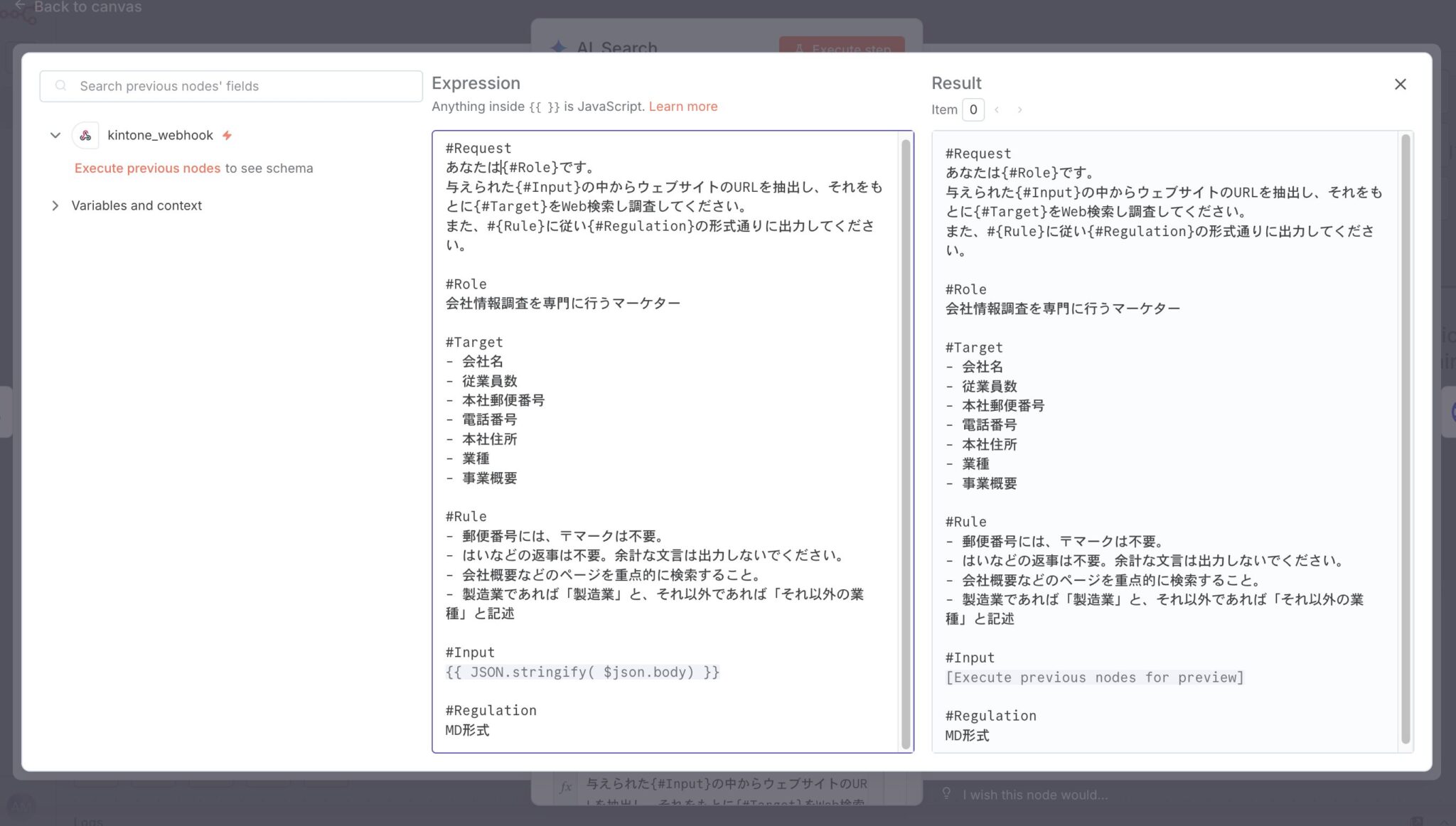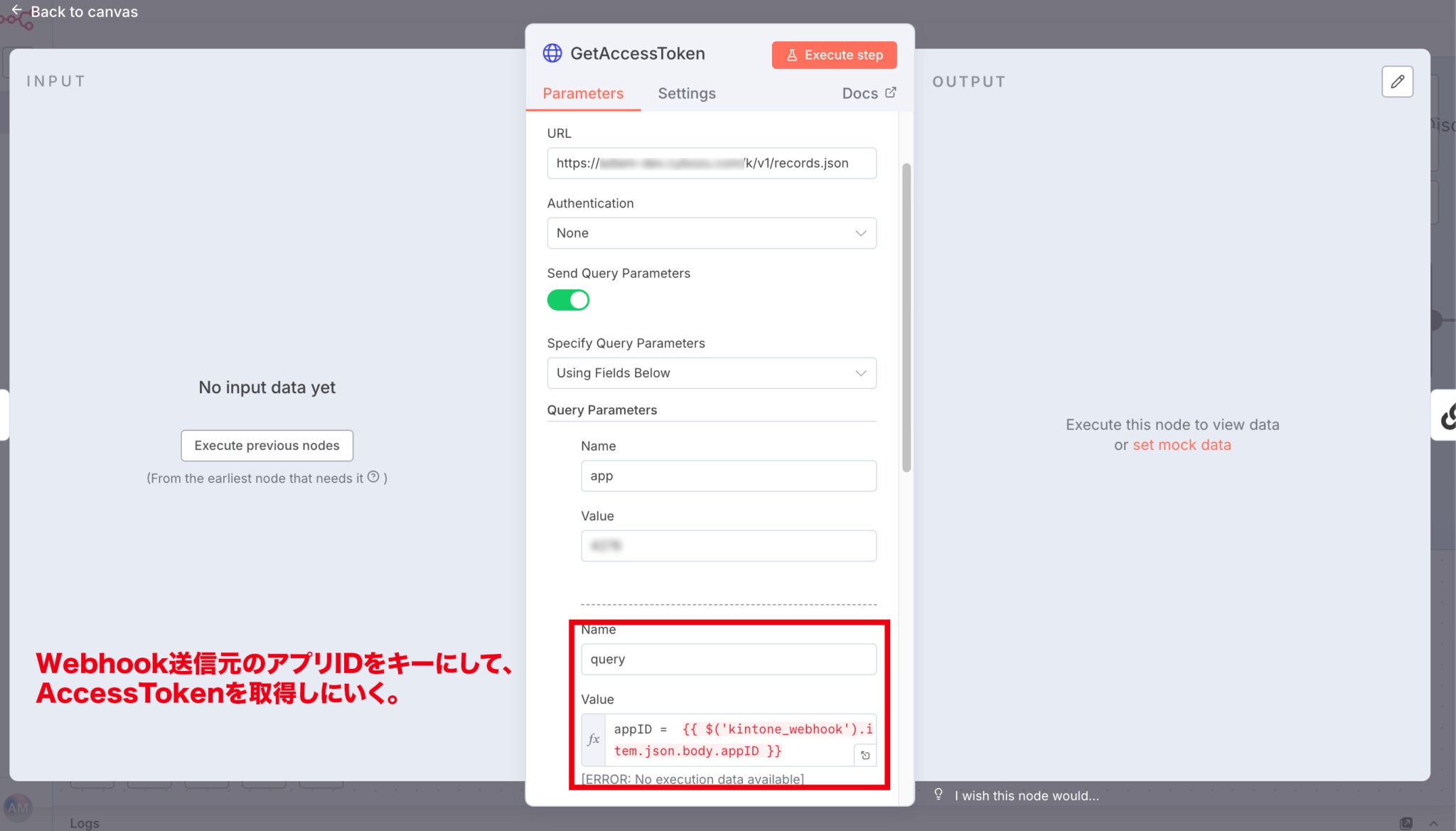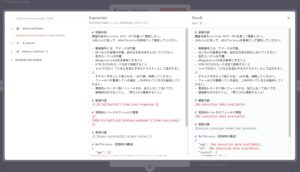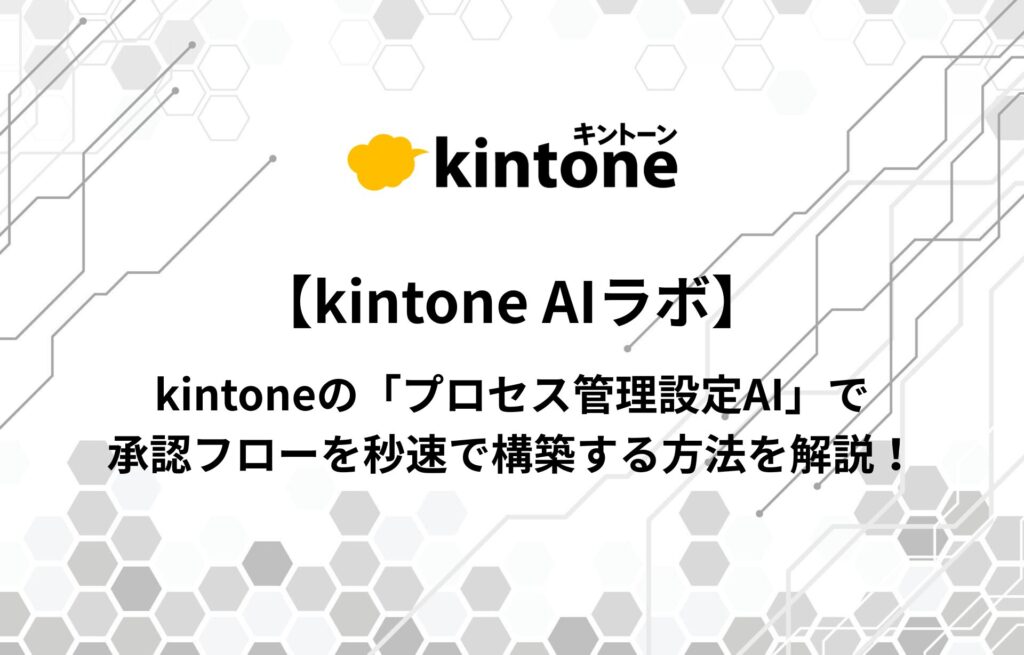目次
はじめに:kintoneのレコードURLを起点に“会社情報の一次調査”を自動化する
本稿では、kintoneのレコードに保存された公式サイトURLを起点にn8nでレコード情報を取得、ワークフローを配線し、生成AIで会社情報調査と要約、kintoneへ書き戻すまでの全体像を解説します。
このワークフローの狙いは「人がやるべき判断に時間を使い、一次調査を任せる」こと。
具体的なAPI値や細かな実装は最小限にし、考え方と運用のコツにフォーカスします。
使う道具と役割(kintone=ハブ/n8n=ワークフロー/生成AI=検索・要約)
kintoneは企業マスタや取引履歴など情報をためるハブとして利用。
n8nは各サービスをワークフローでつなぐ配線係。
生成AIは調査・要約を行い、収集したテキストから要約・抽出・分類、kintone REST APIを使ったレコード更新用のjsonBody生成まで行います。

n8nの特徴
- GUIで可視化されたワークフロー構築ツール。
- Webhook・Cron・HTTP・Slack・メールなどデフォルトで使えるノードが豊富で拡張しやすい。
- セルフホスト可。認証情報(APIキー等)をCredentialsで安全に管理。
- コミュニティノードをインストールする事で、更にノードの拡張が可能。
n8nの料金
- セルフホスト:OSSとして無償利用可(インフラ費のみ)。
- クラウド:無料枠~有償プランまで。実行数や同時実行、チーム機能の有無で選べます。
※価格は変動し得るため、具体金額は公式サイトの最新情報を参照する運用を推奨します。
この自動化で何を調査させるか(収集項目の定義)
ゴールは一次調査。深掘りは人が行う前提で、以下を“最低限のセット”として定義します。
調査対象項目
- 社名(正式表記)
- 本社所在地(都道府県レベル)
- 従業員数
- 郵便番号
- 電話番号
- 事業区分(製造業 or NOT )
- 事業概要
仕組みの全体像(kintone → n8n → 生成AI → kintone/通知)
手順
1.kintoneのレコード情報取得
n8nのトリガーから「Webhook」を選択。
自動的に生成されたエンドポイントをkintoneアプリの「設定」→「Webhook」→「+追加する」にペースト。
※先頭のhttps://は削除すること。
- トリガーにWebhookを選択
- エンドポイントは自動生成
2. URLを生成AIに渡し、会社情報調査を行う。
コミュニティノード「Gemini Search」をインストールし、Webhookノードのアウトプット側に繋げる。
プロンプトに依頼内容、役割、対象項目、ルール、インプット(ここではkintoneレコード内の会社URL)、出力形式を指定する。
3. kintoneアプリのAPIトークンを取得
本例では、後述の手順にてn8n の『HTTP Request』ノードからkintone REST APIを呼び出してレコードを更新します。
必要な APIトークンはkintoneの管理用アプリで一元管理し、アプリIDをキーに取得します。
4. 調査結果をLLMで分類、整形
「Basic LLM Chain」ノードを配置し、Gemini Chat Modelを接続。
そのままでは、n8nがコードブロック付きのJSONを返してくる事が多かった為、試行錯誤しプロンプトにて平文で返却する旨と、出力のサンプルを与える事で回避している。
- Basic LLM Chainノードを配置
- プロンプトにて指示を与えJSONを生成する
5. kintoneへ書き戻す/通知する
「HTTP Request」ノードを配置し、kintone REST APIにて更新を行う。
更にもう1つHTTP Requestノードを追加し、同様にコメントにて通知を行う。
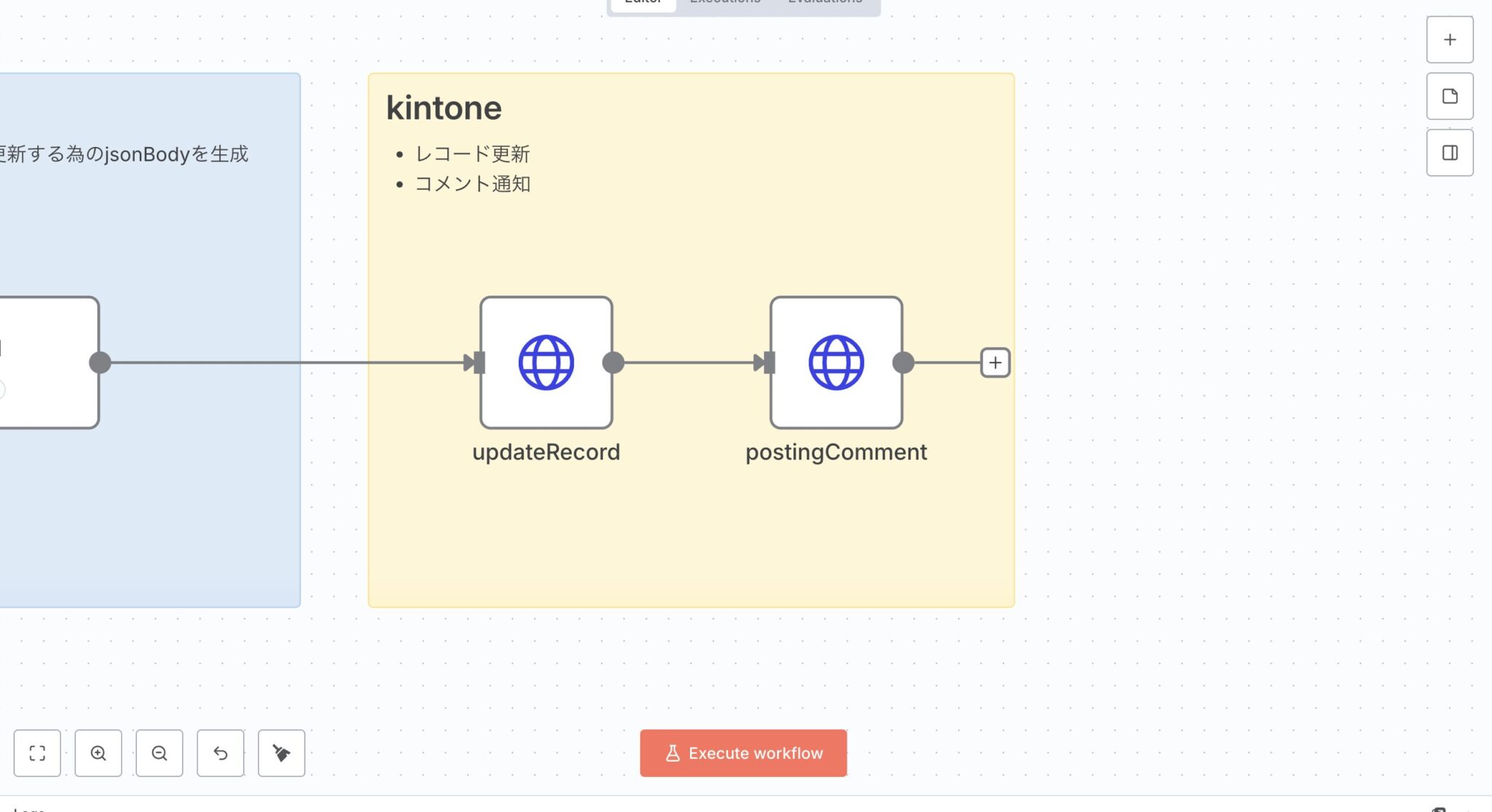
運用設計のヒント(失敗時の扱い・ログと通知)
例外処理(保留フラグ/再実行)
- 取得・AI・書戻しのどこで失敗したかをエラーステータスで記録。n8nの実行IDをkintoneに残すと再実行が容易。
- 404/タイムアウトは自動リトライ上限を設定し、超過時は「保留」に振り分けて人が確認。
検証・改善(精度とコストの見直し)
- 入力を短く、フォーマットを固定が基本。長文はAI前に要約/HTMLは削除。
- 月次で更新件数・失敗率・平均トークンを確認し、ボトルネックを特定。
- モデル切替時は出力スキーマを固定しておけば、下流のkintone側は無改修で済みます。
まとめ(Webhook起点 × 最小構成で小さく回す)
- kintoneのWebhookを起点に、n8nで情報を取得し、生成AIで一次調査。役割分担を明確にすると設計がシンプルに。
- まずは対象を限定して回し、出典保持・例外処理・通知の3点を固める。
- 出力フォーマット固定とログ設計が、保守とモデル切替をラクにします。
kintoneと生成AI(Dify、n8n)で、定型業務を自動化するワークフロー開発サービスを提供開始!
アディエムでは、現場起点の業務改善を支援する「kintone × Dify × n8n」の伴走サービスをスタートしました。
ノーコードツール(kintone、Dify、n8n)を活用することで、
・kintoneの登録・更新・集計
・外部クラウドとの連携の自動化
・生成AIを取り入れた業務フローの最適化
までを自動化し、工数削減とヒューマンエラー防止を実現します。
アディエムでは、特に製造業での生成AI活用事例を増やしたいと考えています。
「こんな業務を自動化できる?」「生成AIと組み合わせたい」など、 ぜひお気軽にアイデアをお寄せください。
最後に
株式会社アディエムでは、kintone × 生成AIで日々の業務改善に取り組んでいます。
今回ご紹介したようなワークフローの他にも、お客様の業務に合った改善をご提案させて頂きます。
無料相談も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。